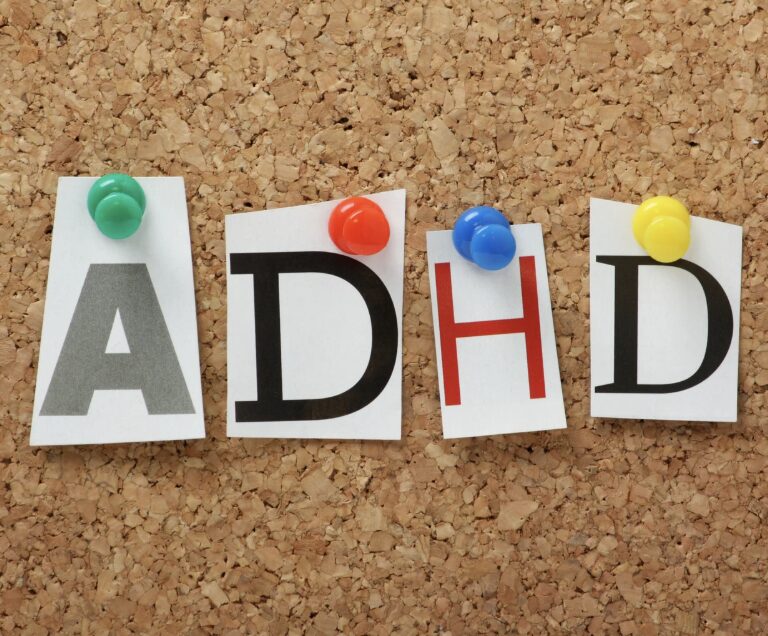大人の発達障害の診断における心理検査の役割と課題
DSM-5・ICD-11の診断基準と心理検査の必要性
成人の自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の診断は、基本的にDSM-5やICD-11の診断基準に基づく臨床評価によって行われます。DSM-5およびICD-11の診断基準は症状の持続や日常機能への影響といった行動面の所見と発達歴に焦点を当てており、特定の心理検査の実施を必須とはしていません 。実際、実臨床における大人の発達障害の診断には主に医師による問診(生育歴や現在の症状の聞き取り)に依拠します 。したがって心理検査を行わずとも診断基準を満たせば診断は可能であり、診断そのものは医師の臨床判断で下されます。
もっとも、DSM-5/ICD-11の診断プロセスでは多面的な情報収集が推奨されています。例えばADHDでは臨床面接に加えて本人や家族・周囲からの評価尺度(質問票)を用いることが一般的であり 、正式な診断にはDSM-5やICD-11の基準を満たすことが必要です 。ASDに関しても、ICD-11解説書では「格別の努力によって多くの場面で適切に機能しているASD者」に対しても診断は適当であると明記されており 、表面的な適応度の高さだけで診断を除外すべきではないことが示唆されています。またDSM-5とICD-11の双方でASDとADHDの併存が認められるよう診断基準が改訂されており 、成人でも両者の合併症例に適切に診断が付けられる体制が整っています。
要するに、DSM-5やICD-11に則った診断は心理検査が必須ではなく、問診や観察から得られる臨床像と発達歴によって診断は可能です 。しかし現実には、診断の精度と包括的な評価のために心理検査が補助的に用いられることが多く、これにより症状の客観的把握や他疾患との鑑別に役立てています  。
診断が難しいケースの特徴
成人のASDやADHDでは、以下のような要因により診断が困難なケースも少なくありません:
• 他の精神疾患との鑑別が難しい:
ASDやADHDの症状は他の疾患と重なりやすく、鑑別診断に苦慮することがあります。例えばASDの対人交流の困難さは社交不安症や統合失調症の陰性症状、強迫症状などと見分けにくく、ADHDの注意散漫や衝動性は双極性障害の軽躁状態やパーソナリティ障害の症状とも紛らわしいことがあります 。実際、ICD-11の解説ではASDの鑑別対象として統合失調症スペクトラムや社交不安症、強迫症など多数の疾患が列挙されており 、ADHDも共存症の多さや症状の重複により評価が複雑になると指摘されています 。こうした鑑別診断の難しさが診断を迷わせる要因になります。
• マスキング(症状の隠蔽・偽装):
特に高機能自閉スペクトラム症の成人では、社会的スキルを後天的に学習して表面的には定型発達者と区別がつかないよう振る舞う方もいます。いわゆる「カモフラージュ」や「マスキング」により幼少期からの特性を隠してきた場合、診察場面でも明らかな対人スキルの欠如が観察されないことがあります 。ICD-11も周囲に適応しているように見えるケースであっても診断を検討すべきと述べているように 、マスキングは診断遅延の大きな要因です。特に知的能力が高く人付き合いのコツを掴んでいる人では、高い知能や努力による代償で症状が覆い隠され、子どもの頃から見逃されて成人に至るケースもあります 。
• 本人の自己認識の乏しさ:
ADHD成人の中には自らの症状や困難さを過小評価している例があり、自覚症状の訴えが少ないため診断が見過ごされることがあります 。実際の研究でも、成人ADHD当事者は注意欠如や多動衝動の症状を自己報告では軽く見積もる傾向が示されており(臨床評価との不一致) 、自己評価だけに頼ると症状の把握を誤る可能性があります。同様にASDでも、自分の対人困難に気付かず「誰でも人付き合いは苦手なものだ」と捉えていると、専門家に相談する機会が遅れ診断が遅滞する場合があります。自己洞察の欠如は支援に繋がるハードルとなり、他者から指摘されて初めて評価につながるケースも多いです。
• 発達初期の情報不足:
DSM-5やICD-11の診断基準では、症状が発達早期(ASDでは幼少期、ADHDでは12歳以前)に現れていることが条件とされています。しかし成人になってから振り返る場合、幼少期の記憶があいまいだったり、両親や保護者から十分な情報が得られなかったりして、発症のタイミングや当時の症状を裏付けるエビデンスが不足することがあります 。例えば幼少時の報告書や成績表、母子手帳などの客観資料が無い場合、医師は「小さい頃からの症状の連続性」を確認できず確証を持って診断を下しにくくなります。このような発達歴情報の欠如も診断を難しくする一因です 。
• 環境要因による症状の非顕在化:
症状や特性はあっても、本人を取り巻く環境が非常に順応的・支援的であるために生活上大きな支障が表面化していないケースもあります。そのような場合、診断基準にある「社会生活上の困難さ」が明確でないため、医師が積極的に発達障害の診断をつけることを控えることがあります 。例えば得意な分野の職に就いて周囲の理解も得られている場合、対人関係や仕事上の問題が顕在化せず、診断に必要な臨床的障害の基準を満たさないことがあります 。このように症状による支障が顕在化していない(グレーゾーン)ケースでは診断が見送りとなりやすい点にも留意が必要です。
以上のような要因が重なると、成人のASDやADHDの診断は専門家でも容易ではないことがあります。実際、成人期に至るまで発達障害が見逃されてきた背景には、症状が軽微であったり周囲に溶け込んでいたり、あるいは他の診断名で説明されていたりするケースが多いと報告されています 。このため、困難例では慎重な情報収集と経過観察、複数回の評価面接が必要になる場合もあります。
困難例における心理検査の有用性
診断が難しいケースでは、心理検査を活用することで追加の客観情報を得て診断精度を高められる可能性があります。ただし心理検査はあくまで診断を補助する手段であり、結果の解釈は臨床的文脈と照らし合わせて慎重に行う必要があります 。以下に、心理検査の主な役割と有用性を整理します。
• 症状評価の客観化と多角的な情報収集:
質問紙や評価尺度を用いることで、本人の自己評価だけでなく周囲からの観察情報を数値化できます。例えば成人ADHDの評価にはASRSやCAARSなどの自己記入式チェックリストが用いられ、配偶者や同僚からの他者評価も取り入れることで主観的な偏りを補正します 。ASDでもAQやCAT-Qなどの自己報告尺度のほか、親やきょうだいへの聞き取りや他者からのフィードバックを集めることで、本人が気付いていない特性や幼少期からの一貫した症状を浮き彫りにできます 。このようにマルチインフォーマント(複数情報源)からのデータは、マスキングや自己認識の問題があるケースで診断の裏付けとして有用です。
• 発達プロフィールや認知機能の把握:
知能検査や神経心理学的検査によって、その人固有の認知の凸凹(プロファイル)を評価できます。例えばWAIS-IV(ウェクスラー成人知能検査)は知的能力全般のみならず作動記憶や処理速度などの指標を提供し、ASDやADHDにしばしば見られる認知の偏り(例:言語理解と非言語推理の差、処理速度の相対的低さ)を捉える手掛かりになります 。ただし知能検査は診断確定のためではなく、支援計画や他の障害との鑑別補助の目的で実施されます 。また、注意機能を客観評価する連続遂行試験(CPT)などもADHDの注意障害を定量化できますが、注意機能低下はうつ病や不安障害など他の要因でも起こり得るため特異度は高くなく、結果の解釈には注意が必要です 。実際、CPTはADHDを持つ成人で高い感度を示す一方、多くの中枢神経系の問題で成績が低下しうるため、単独では診断の決め手とならないことが指摘されています 。
• 構造化された診断的評価ツール:
専門家が実施する構造化面接や観察式の検査も有用です。ASDではADOS-2(自閉症診断観察スケール)やADI-R(自閉症診断面接)といった「ゴールドスタンダード」とされる評価法があり、標準化された手順で社会的コミュニケーションや行動の特徴を引き出すことができます 。これにより、日常会話では見落とされていた自閉症スペクトラムの所見が明確になる場合があります。ただし注意すべきは、ADOSの所見はASDに特異的とは限らない点です。研究では、成人の精神科症例にADOS-2を実施したところASDの感度は高かったものの、精神病症状のある患者に30%の偽陽性(誤ってASDと判定される)を示したと報告されています 。つまり、ADOSで社会的やりとりの困難が観察されても、それが統合失調症など他の疾患による可能性もあるため、検査結果を鵜呑みにせず臨床像全体を考慮する必要があります 。ADHDに関しては、成人用の構造化面接ツール(例:DIVA-2など)が開発されており、幼少期から現在までの症状を体系立てて確認できます。これらは診断基準の充足状況を漏れなくチェックできる利点がありますが、やはり結果は面接者の技量や情報源の信頼性に左右されるため、他の情報と総合して判断します。
• 他の障害の鑑別と併存症の評価:
困難例では、発達障害以外の疾患が隠れていないか、あるいは併存していないかを評価することが重要です。心理検査はその助けとなります。例えばうつ病や不安症のスクリーニング検査(質問票)を併せて行い抑うつ傾向の有無を把握したり 、ASDとADHDの特性を多面的に評価するマルチプロファイル検査(日本版のMSPAなど)で発達障害以外の要因で説明できる症状がないか検証したりします 。必要に応じて脳波検査やMRI等で他の神経疾患を除外することもあります 。こうした追加検査の結果は総合診断(integrated diagnosis)の材料となり、発達障害の診断根拠を強化すると同時に、他の疾患の見落とし防止につながります。
以上より、心理検査は診断に迷うケースで有益な補助情報を提供しうるものです。定型化された指標やデータによって主観に頼らない視点を加えることで、診断基準の充足状況を裏付けたり 、特性の程度や日常生活への影響度を定量化して臨床的判断をサポートします 。ただし繰り返しになりますが、心理検査の結果のみで診断が決まるわけではなく、必ず医師による臨床面接の所見や病歴、家族からの聞き取り情報などと併せて総合的に判断されます 。心理検査はあくまで補助的手段であり、その役割は「診断を下すこと」ではなく「診断の裏付けや支援策立案の材料を提供すること」にある点に留意が必要です 。
ガイドラインおよび臨床実践における心理検査の位置づけ
国内外のガイドラインや専門家の見解においても、心理検査は診断の補助ツールとして位置づけられています。診断基準そのものはDSM-5やICD-11に準拠しつつ、より信頼性の高い評価のために必要に応じて心理検査を活用するというスタンスです。
• 国際的ガイドライン:
例えば英国のNICEガイドラインでは、成人のASDやADHDの診断について専門家チームによる包括的アセスメントを推奨しています 。具体的には、十分な臨床診察と心理社会的評価、発達歴の聴取、本人および家族からの報告に基づき診断すべきとされ 、必要に応じて標準化された評価ツール(AQ-10などのスクリーニングやADOS/ADI-Rなどの診断的検査)の利用も言及されています 。NICEの成人ASD指針ではAQ-10(自閉症スペクトラム商務10項目)で一定以上のスコアなら専門評価を行うこと、評価時には他の併存症の有無を確認し(必要に応じて formal assessment tools を用いる)と記載されています 。ADHDについてもNICEは診断は精神科医など専門医が行い、評価にはDSM-5の基準への適合性を確認すること 、および複数情報源から症状を評価する(成人では配偶者や同僚からの聞き取りを含める)ことを推奨しています 。米国においてもAPAや各専門団体から、成人の発達障害診断では医学的評価とともに心理学的評価を組み合わせる包括的アプローチが推奨されており 、診断の信頼性向上と見落とし防止のための多職種連携が重要視されています。
• 国内の指針・臨床実践:
日本でも、発達障害者支援法や関連ガイドラインに基づき、医療機関での診断と多職種連携による支援が謳われています。診断プロセスに関する一般的な解説では、まず精神科医による問診・診察を行い(現症の把握と幼少期の様子の聴取) 、次に必要に応じて発達検査・知能検査・人格検査などの心理検査を施行し、最終的にそれらの情報を統合して診断を下すという流れが示されています 。重要なのは、ここで「心理検査をしないケースもあり、実施する検査の種類は病院の方針や医師の判断によって異なる」と明記されている点で 、心理検査は必ずしも全例で実施されるものではなく各症例のニーズに応じて選択されます。また日本発達障害学会や関連学会から公式の診療ガイドライン(例:『ADHDの診断・治療ガイドライン第5版』等)が公表されていますが、その中でも診断はDSM-5(またはICD)基準に則って臨床的に行うことを基本としつつ、必要に応じて心理検査や評価尺度で補足評価を行うことが推奨されています 。例えば成人ADHD診断の指針では、医師による現在症状と幼少期症状の丁寧な聞き取り、社会機能障害の評価(心理検査や尺度の活用)、鑑別診断の検討といったステップを踏むよう提言されています 。ASDについても知的能力や言語発達水準の評価を付記することが求められており 、知能検査結果などはその情報として扱われます。
• 多職種連携の重要性:
臨床現場では、発達障害の評価・支援に精神科医だけでなく心理士や作業療法士、ケースワーカー等が関与することが望ましいとされています。心理検査の多く(知能検査やADOSなど)は公認心理師・臨床心理士といった専門職が実施し、結果を医師と共有して診断や支援計画に活かします。多職種チームで協働することで、医学的視点(鑑別診断や薬物治療方針)と心理社会的視点(行動特性や環境調整方針)を統合した包括的なケアが可能になります。ガイドラインでも、ASDの診断は必要に応じて発達障害支援センター等とも連携しながら進めることや、診断後は福祉・就労支援機関と協働して支援計画を立てることが推奨されています 。つまり、診断自体も多職種の知見を活かした総合的なプロセスであり、心理検査はその中の一要素として適切に位置付けられます。
総括すると、心理検査は成人ASD・ADHDの診断において補助的に用いるべき手段であり、必須項目ではありません。診断基準に合致するかどうかは最終的に臨床医の総合判断によりますが、心理検査の結果はその判断を裏付け、あるいは難治ケースで視野を広げる助けとなります。国内外のガイドラインも、こうした心理検査の有用性を認めつつも診断の拠り所はあくまで臨床評価であることを強調しています 。したがって実践においては、まず診断基準に沿った丁寧な問診と観察を行い、必要に応じて心理検査で情報補完し、医師が多職種チームの知見も踏まえて総合的に診断するという形が理想的です 。このアプローチにより、見立て違いや見落としを減らしつつ、診断後の支援に直結する実用的な評価が可能になると考えられます。各専門職が連携し、エビデンスに基づきつつ個々のケースに即した柔軟な評価体制を敷くことが、成人のASD・ADHD診療における質の高い診断・支援につながるでしょう。
参考文献
1. DSM-5(2013): 米国精神医学会発行の精神疾患分類。ASD/ADHDの診断基準が詳細に示されており、国際的に用いられる。
2. ICD-11(2019): 世界保健機関(WHO)の国際疾病分類。ASDとADHDを神経発達症群として位置づけ。
3. NICEガイドライン: 成人ASD (CG142)、ADHD (NG87) など、症状評価と多職種連携アプローチの推奨。
4. 日本国内ガイドライン: 精神神経学会などが作成したADHD診療ガイドラインや発達障害関連指針。心理検査は補助的役割があるが、診断自体は臨床総合評価で行うと明記。